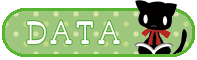ぎょくおん

共依存めいた関係にあった姉から逃げるように東京を離れ、さびれた温泉街の旅館で住み込みの仕事を始めた男・郡司。
いっさいの連絡を絶って一年になろうとしていたが、心は吹っ切れない。 また、常用している薬の副作用による乳汁分泌に悩まされ、消極的な死に憧れを見出していた。
ある日、姉とそっくりな少女と出会い、郡司はひどく混乱する。
「──あれは姉の生霊だ。おれの戦争はまだ終わっていなかった」
妄想を克服しようとするうち、旅館の社長の姪・七美から秘密を打ち明けられたり、同僚・アランと関係したりする。
やがてゲンバクよろしく、郡司に降ってきた圧倒的な痛みとは──。
※男性の母乳、同性・異性間の性行為に関する描写を含みます。
とはいえ直接的・詳細な性表現はありませんので、年齢制限は致しません。
逆にそういったえろすを期待して読むとがっかりすると思います…。
総じて、だめな男がうだうだしている話です。
(Text-Revolutions Webカタログより転載)

オカワダアキナさんの「ぎょくおん」を読んだ。オカワダアキナさんの物語に惹かれたのは、textrevolutions3の公式アンソロジー「猫」に寄稿されていた小説を読んだことと、同イベントのサークル紹介に惹かれたから。
サークル紹介にはこうある。
「ジョバンニやカンパネルラになれない人たちの物語を綴っているので、ザネリといいます。日常をうっすら逸脱した話を書いています」
「ジョバンニやカンパネルラにはなれない人」として挙がる「ザネリ」。主人公にはなれなかった登場人物、という見方もできるだろうが、宮沢賢治「銀河鉄道の夜」では、ザネリを助けようとしてカンパネルラは溺死した。いつもジョバンニに視線を向けながら、それでもザネリと連れ立っていたカンパネルラ。
ザネリは、主人公として語られることはなかったけれど、ものがたりの神に後ろ暗く、もっとも祝福されていたのではないかと思うことがある。
サークル紹介を読んで、まっさきにそう思い、さらに「ぎょくおん」というタイトル本をつくる、という。
「ジョバンニやカンパネルラになれない人」がきく、「ぎょくおん」。表紙をひらくまえから、その凄絶さに打ちのめされそうになってしまう。
「ぎょくおん」というタイトルから、想起されるのは第二次世界大戦、つまりは戦争なのだけれど、物語の舞台は七十年前、ではない。主人公はスマートフォンを使わないけれど持ってはいて、Twitterもある。主人公湯田郡司は抗精神病薬を飲んでもいる。――それなのに、現在住み込みではたらく温泉旅館に来た理由は、「ただひたすらにバクダンから逃げてここまできました。」
物語は、郡司の淡々とした独白で語られてゆく。先の大戦の映像のようにモノクロで、動きにちょっとずつひっかかりのある語り口。そうして語られる、「バクダン」が降っているのは、姉に養われていた都会だ。
郡司にとって、姉のヒモとして生きてきた都会はバクダンの降る戦時下なのだ。
ヒモという暮らし、労働から離れ世間のわずらわしさから解放された気ままな生活。一見すると他者に養われて生きるのは気楽で羨ましくもあるだろう。
けれど、渦中にあるものにしては、一種の戦争なのでは、と思う。
おのれが銃をもったり、戦闘機に乗りこんだりする、能動的な戦争ではなく、空襲警報やB29の影におびえる、受動的な戦争。
個人的な話をする。職を失って生きていたとき、ずっと家族のゴキゲンをうかがって生きていた。それはもう、貯金があるとか、定期的に金を入れている、とかそういうこととは関係がない。たとえば、具合が悪くて朝九時過ぎに起きてきたとき、たとえばただ、爪を切っていただけ、そういう何気ないきっかけで、「生かされている」「生かしていただいている」自分を思い知ることになる。それは、たしかに空襲だった。――その空襲には、空襲警報があるときもあるけれど、ないときのほうがほとんどだ。
おなじときに、定職を持たずにいる、ひとり暮らしをしている知人と話をする機会があった。かれは、自分をのみ生かし、自分をのみ維持すればいい。誰のゴキゲンをうかがうこともなく、粛粛と日常を重ねていた。おなじ職なしで、同じように貯金を切り崩して生きて、ただ、家族がいないだけで、ひとりだというだけで、かれは、突然の空襲からは隔絶されていた。
わたしは、郡司が「バクダンから逃げてここまで来ました。」という、そのバクダン、について考える。
家族のいること、それも、家族に養われていること、は戦争だ。一挙手一投足をつねに家族に監視され統制された身辺。冗漫でけれど確実な。金品は配給制だろう。配給を得るための切符がなになのかははっきりとは語られないけれど、空襲を運よくかいくぐらなければ得られぬたぐいであるのは、なんとなく、わかる。
姉と性的な行為(でもねえさんとは兄弟であるからセックスではありません)をくりかえしていることも、飼っていたクラゲが死んでしまったことも、ちいさなバクダンだ。「毎日毎日、点を描いて暮らしてい」ることは、バクダンから生き延びるための、なんとかして自分を守るためのことだ。
――爆風で割れたガラスを全身に浴びてしまった人が、ずいぶん後になってから手術を受けたら、からだに入りこんでしまったガラス片に脂肪がまいていた、という話をなにかでよんだことがある。なんの本だったかは忘れてしまったが、そこだけはおぼえている。
「バクダンから逃げて」温泉旅館に住み込みで働き始めた郡司が見る女のまぼろしは、脂肪のまいたガラスのようだと思う。入りこんだ異物から内臓やその他のぶぶんを守ろうと巻かれた脂肪。けれど、脂肪のなかにはかならず、凶器が、からだの害になる物質がたしかに存在していて、分解してしまうことは不可能なのだ。
バクダンから戦争から疎開してきた郡司が最後に受ける攻撃。そして最後に聞く、「ぎょくおん」。――郡司の戦争は、「終り」はしても「玉音放送」を聞くかぎり、敗戦だ。待ち望んだ敗北。ポケットにひそみつづけた飴玉はバクダンで、噛み砕くとあっというまに溶けて体内のいたるところにひそむ。
そのバクダンの破片も、郡司のなかで幾重にも脂肪が巻かれるのだろう。戦争の爪痕は消えない。身体の作用につつまれて、けれどもたしかな凶器として、そこにのこりつづける。