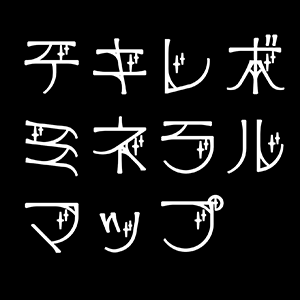丘の上のありす
あたしは今、はじめて訪れる街にいる。
目の前には蜘蛛を模した大きなモニュメントと円錐状の高層ビル。隣には初対面の少女がひとり。人見知りで内気なあたしが、見知らぬ誰かと見知らぬ街に足を運ぶだなんて、普段であればするはずがない。どうして、こうなってしまったのだろう。一時間前のあたしには想像できない状況だった。
ありすと出会う前、あたしは緑が丘公園のベンチで本を読んでいた。江ノ島で会った二匹の黒猫を思いだし、図書館で一冊の児童書を借りた。猫が書いた文章をひとの手で清書したという作品、『ルドルフとイッパイアッテナ』。あたしが生まれる前に書かれた作品なのに、読み書きができる黒猫の物語は今読んでも新鮮に感じる。何度も読んだ本なのに不思議と色褪せない。
物語の世界に没入していると、不意に声をかけられた。それがありすだった。フルネームで各務ありす。夢村月海と書いて「ゆめむらつぐみ」という名前のあたしがいうのも変だけど、すごい名前だ。
「ねえ、六本木ってどこ?」
ありすの言葉を理解するのには時間がかかってしまった。あたしがいるのは東京都練馬区にある住宅街。六本木は港区にある。地下鉄で乗り換えなしに行ける街だけど、少なくともここで道を訊くべき場所ではない。しかも、本を読んでいるあたしに。
駅の場所を伝えてもありすは軽く肩をすくめ、
「東京って全然わかんないんだよね。私、岐阜からきたんだ。ね、案内してよ」
あたしの手を握り、半ば強引にベンチから立たせる。もちろん拒否してもよかったのだけど、断れなかったのはありすがだした地名のせい。岐阜は黒猫ルドルフの出身地だった。
──そして今に至る。
ありすに手を引かれ六本木ヒルズを歩く。目に映る光景は異世界だった。基本的に自宅と高校と図書館だけが生活圏になっているあたしには縁のない世界。ビルのなかは未来的で迷路のような空間になっていて、名前だけは知っているブランドのお店や美しすぎて我が家には不釣り合いな家具や雑貨のお店が並ぶ。時計うさぎを追いかけて不思議の国に迷いこんだような、魚屋さんから逃げるうちに東京まできてしまった子猫のような、そんな心境になる。
その異世界をありすは少し駆け足で歩く。どこか目的地があるのか、それともなにかを捜しているのか、まわりの景色を楽しむ様子もなく奥へ奥へと進んでいく。最初から案内なんて必要ないように、どんどん先へ。
だから、なんとなくわかってしまった。先日の江ノ島のこともあったから、その連想でもあるけれど。
「ありすさん」あたしは足を止めて声をかけた。
「さんはやめてよ。同い年なんだから」
あたしは苦笑いをした。さんづけは癖のようなもの。出会ったばかりのひとには無意識に「さん」とつけてしまう。
「それで、なに?」
ありすの顔は少し強ばっていた。焦っているような、余裕がないような。その表情をみて、でかかっていた言葉を呑みこんだ。代わりに別の科白をいう。
「ちょっと休もう。あたし、喉かわいちゃった」
逡巡したあと、ありすは頷いた。
「……そうだね」
歩いて気がついたけど六本木ヒルズにはカフェが多い。目についたお店に入り、あたしは紅茶を、ありすは珈琲を注文する。席に着いたあとも、ありすはお店の外を気にしているようで落ち着きがない。
ねえ、と声をかけてようやく正面をむいた。心ここにあらずという感じ。思わず溜息がこぼれた。
「六本木にくるのに、あたしに声をかけたのはどうして?」
と訊いてみる。予想外の言葉だったのか、「答えづらいこと訊くね」とありすは苦笑いする。
「理由はいろいろあるんだけどね。六本木の行き方がわからないのも本当だったし。でも、一番の理由は杉浦範茂さんのイラストがみえたからかな。『あ、ルドルフだ』って」
「ありすも本を読むの?」
「多少ね。こんな名前だし」
ありすは何人かの作家をあげた。ルイス・キャロル、J・K・ローリング、上橋菜穂子、荻原規子、はやみねかおる。なんとなく読書傾向がわかる名前。
「それとね、つぐみをみて直感したんだ」
「直感?」
「うん。この子とは友達になれるって。それがつぐみに声をかけた理由。おかしいかな」
「変じゃないよ」と首を振る。
ありすのいう直感は多かれ少なかれ誰もが経験しているもの。もちろん、あたしも。図書館や本屋さんで並んだばかりの本の表紙をみたとき、実際に手にとってページを捲るとき予感することがある。あたしは絶対にこの本が好きになる、と。そして、その予感はだいたい外れない。一目惚れに近いといっていいかもしれない。ひとと本というちがいはあるし、ありすの場合は恋という感情ではないけれど。
「よかった」とあたしはいった。「そんな素敵な理由があるなんて全然想像してなかった。もっとちがう理由で声をかけたんだと思ってた」
「どんなふうに思ってたの?」
「ひとりだと心細いから。恋人と再会できても、再会できなくてもひとりはつらいから、誰でもいいから声をかけられたのかなと思ってた」
「えっ?」
声が裏返った。目をしばたたかせてあたしの顔をみる。やがて大きな溜息をついてから、ありすは困ったように笑った。
「初対面なのに見透かされちゃってるね。一弥のことは一言も話してないのに、そんなにわかりやすく表情にでてた?」
もう一度、あたしは首を振る。焦りが顔にでていたのは確かだけど、そこから恋人のことまではさすがに読み取れない。
「けど、わかりやすかったかな。ありすの様子は観光目的にはみえなかったし。どこか目的のお店があるなら、事前に場所を調べてたり、誰かに場所を訊くだろうし。それをしないということは捜し物はひとだと思って。捜すひとは誰かと考えたら、恋人が自然でしょう?」
「そうだね」
ありすは力なく頷いてから珈琲に手をのばした。一口飲んで「苦い」と顔をしかめる。
「心細いというのは、もちろんあるよ。知らない場所でひとりはきついもの。だからって、それがつぐみに声をかけたわけじゃないよ?」
「うん。わかってる」
同じ立場だったら、あたしはどうしただろう。不思議の国に迷いこんで、目の前であたしの好きな本を読んでいるひとがいたら。おそらく他のひとではなく、本を読んでいるそのひとに道を訊ねるような気がする。
「あたしも一緒に一弥さんを捜すよ」という言葉にありすは躊躇いもなく首を横に振った。予想外の返事に驚いた。
「ふたりで捜してもみつからないよ」
聞けば、一弥さんは半年前から連絡が取れなくなったという。多少の遅れはあったものの、それまでは頻繁に連絡をしていたのに突然の音信不通。その遠距離恋愛の相手の職場が六本木ヒルズにある。
「どんな場所か一目みたくてきたけど、駄目だね、実際にきたら必死で一弥を捜しちゃう」
「しかたないよ。それだけ好きだったってことだから」と頷いてから、ひとつの疑問を口にだした。「一弥さんの会社には行ってみないの?」
「セキュリティが厳しすぎて無理。一弥の他に知り合いもいないし。それに仕事も辞めてると思うんだ」
「そうなの?」
「たぶん、ね。つぐみと会う前に一弥の住むマンションに行ってみたんだけど、郵便受けの名前が変わってた。部屋を引き払ってるんだよ。だから捜すとしたら日本中になる。つぐみが一緒に捜してくれても、ふたりで捜しだすのは不可能だよ」
「そっか……」
かける言葉がみつからなかった。安易な励ましは、ひとを傷つけることをあたしは知っている。「大丈夫」や「絶対みつかるよ」なんて無責任な科白は口にだせない。
「ありがとね、つぐみ」ありすは優しく笑い、あたしの頭を軽く撫でた。「外にでよっか」
円錐状の高層ビル──森タワーからでて広場をゆっくりと歩く。夏休みという季節柄か、それとも元々なのか観光客が多い。あたしたちと同じ年代の女の子たちが、遠目にみえる東京タワーを歓声をあげながら写真を撮っている。キャリーケースを引いて歩く老夫婦がいれば、森タワーを背景にして記念撮影をしている恋人たちもいる。
観光客以外にもいろいろなひとがいる。ベンチに腰をかけてお弁当を食べているひと。六本木ヒルズが職場なのか、スーツ姿の男性の集団。犬の散歩をしている美しい女性。モデルさんなのか、大がかりな機材で写真撮影をしているグループもいる。
胸が痛くなった。隣にいるありすの手をぎゅっと握る。
あたしの視界に映るひとは笑顔が多かった。全員が笑っているわけではないけれど、少なくとも誰も不幸そうな顔はしていない。ひとり以外は。
「ね、つぐみ」とありすが訊く。「私、どうすればいいのかな。彼の帰りを待ってていいのかな」
ありすと同じ境遇の女の子をあたしは知っている。その物語をさっきまで読んでいた。黒猫ルドルフの飼い主の女の子。
「ありすはルドルフの二巻って読んだ?」
「続きあるの?」
「あるよ。四巻まででてる。今度映画にもなる」
「嘘でしょ」
目を丸くするありすをみて、つい吹きだしてしまった。映画化の話を聞いたとき、あたしも同じ反応をしてしまった。四巻がでていると知ったときも驚いたけど。
「ネタバレになるけど、リエちゃんはルドルフの帰りを待ってたんだよ。だから、ありすも待ってていいと思う」
「そうなんだ」とありすは笑う。「じゃあ、私も待っていようかな」
「うん。それでいいよ」
大事なことは、あえて伝えなかった。「それ」を決めるのはあたしじゃない。ありすが彼女と同じ決断をしても、しなくても、誰もなにもいえない。
ありすの恋の行く末は霧のかかった夜道のようで先が視えない。だから、せめてありすに確かな未来をあげたかった。些細な、けれどしあわせな未来を。
「ね、ルドルフの映画は一緒にみよう。そのときは岐阜まで行くから。約束だよ」
「うん。約束」
指切りをしたありすは嬉しそうに微笑した。
CafeCappucci(Twitter)直参 C-08(Webカタログ)
執筆者名:ひじりあや一言アピール
本の虫たちによる本をテーマにしたアンソロジー『僕らはいつだって本の虫なのサ6』をだします。今回の作品の前日談にあたる物語や、坂口安吾やカフカをモチーフにした物語を収録しています。また、この主人公の他の物語をまとめた個人誌もあります。