青い幻燈(2)

一瞬に魂を燃やす、若者たちの青春
19世紀パリ、ラテン区。画家と詩人が同居する古いアパルトマンに、ひとりの少女がやってくる。ただグリゼット(お針子)とだけ名乗る彼女は、詩人がかつて作った物語のヒロインのようでもあり、画家が愛していた猫のようでもあり……。そんな彼らの前に、永遠の孤独と引き替えに芸術家の魂の充足を約束しようという謎の紳士が現れる。
(第6回Text-Revolutions Webカタログより転載)
※過去の感想はこちら
青い幻燈

私は常々「人間は誰でも一冊の書物を書くことができる(自分の人生という物語について)」という言葉を疑いがちで人間の人生なんていう冗漫なものを物語にするなんてつまらん行為だと思っていた。
そして、もっと悲しいことに、大きな物語が語られるとき、その人の「人生」に焦点を当てたのならばクライマックスにあたる部分が、実は全く物語では語られる必然がない、割愛される部分である、ということは多々ある。……登場人物の「生きた」ことよりも、「物語」されることが優先されねばならない。この感覚はもどかしくて、大きな物語だけでなく、そこからこぼれた番外編を拾ったような書物を作ってくれないかと望んだり、ときに、二次創作というかたちで自ら補完を試みることもある。登場人物の物語を、人生にしようとして。
と、ここまでは長い長い前置き。
ようやく、『青い幻燈』の話をする。
時は十九世紀パリ、ラテン区。登場人物は、画家、詩人、先生、名前のないお針子少女、それから孤独という名の男。十九世紀のパリの薄暗い華々しさと、(今は売れない)画家や詩人という登場人物。読者は、なんとなく、画家か詩人のどちらかは名声を得、売れっ子になってゆくのかな? とか、お針子娘と結ばれるのかな? とか「物語」を無邪気に期待する。だが、詩人も画家も、自費出版した詩集を売り込もうと粉骨砕身したり、自らの血を絵具にしたような絵でコンクールに挑んだり、そんなことはしない。ただおしゃべりをしたり、街を歩いたり。無邪気な期待はあっさりと裏切られる。
おや? と思いながら読んでいく。
なぜなら私は物語を読んでいるのだ。
これは、きっと「何かが起こって」「なにかがきっちりとめでたしめでたしの枠におさまってくれるはずだ」。
そんなことが起こらないことは、作中の人物によって既に語られてしまっているのに、期待をしてしまう。
一部引用をする。
「グリゼット、君は結末のない物語に価値がないと思うかね」 (中略)「それでも、途中の部分がそれはそれは面白い。だから儂は、物語の結末には一般に言われているほどの価値はないのではないかと考えている。結末などなくとも、物語は途中の部分にこそ意味があるのだ」
物語を読むとき、読み手は「結末」を求める。予想できなかったどんでん返しを、期待通りの大団円を、とにかく「ちゃんと終わってくれること」を望み、「結末」に優劣までつける。
そりゃあ「物語」を読むんだから、ちゃんと始まってちゃんと終わってくれないと困る。
ただ、私はここでいちど、立ち止まってしまった。
この物語は、「終わらない」ことを語ろうとしているのではないか、と。
私はここまできてようやく、並木陽さんの、流れる時間のどこに焦点を当てているか、そのまなざしを発見したのだ。
『斜陽の国のルスダン』や『ノーサンブリア物語』のように華々しく語られる主人公たちの人生の物語ではあえて「語ることを控えられた」人たちの「物語」を、このひとは取りこぼしてはいなかったのだ、ということを。
『青い幻燈』の登場人物はルスダンやアクハのように、物語の主人公として語られるべき人々とはちがう。きっとその人生は「物語として語られることは決してない」人たちだ。「物語にはなれない人たち」と言い切ってしまってもいい。
彼らの人生を一から十まで語られたら、きっと冗漫でつまらなくて「読めない」。
でも、その途中には、物語の登場人物当人すら気づかない人生のクライマックスがある。そこだけを切り取れば、きらきらと輝いて「物語」としての強度を持つものが。
『青い幻燈』は、誰もが物語の始まりと終わりを抱えて生存している証のような書物だと思った。その始まりと終わりがどれだけ平凡で語るに足らなくとも、一瞬を切り取ることはできて、劇的な始まりも終わりもなくても語るに値するのだ、ということを発見する足掛かりというか。
これは、物語を語ること・読むことにとらわれている人間が、始点と終点を必要とする物語の義務と責任から自由になるための書物。(「グリゼットこそは、貧しくともこの世で最も自由な女なのだから。」という一文はとても印象的)
どこからきてどこへ行くのか、そこに物語性がなくともあらゆる人間は一冊の書物を己のうちに抱えている。その生きた軌跡は語るに値するものなのだ。
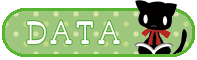
発行:銅のケトル社
判型:文庫(A6) 56P
頒布価格:500円
サイト:なし
レビュワー:孤伏澤つたゐ

